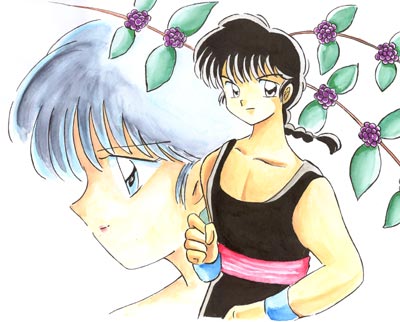
注/この作品の乱馬とあかねは拙作長編「蜜月浪漫」の二人です。多分。
紫の君へ
「今度の雑誌のインタビュー、万事よろしくね。」
そう言ってなびきが笑った。
「ええ?インタビューとかトークとか好きじゃねえの知ってるだろぉ?」
思いっきりしかめっ面をしてやると、
「何言ってんの。格闘家とて人気稼業には違いないのよ。ファンはあんたのベールの下、を少しくらい見てみたいもの。イメージアップにも繋がるし、今更逃げないでよね。」
と素気無く言葉を打ち返された。
「ちぇっ!面倒臭え…。」
今の俺、二十五歳。格闘家として、年齢的にも経験的にも脂に乗り切った頃合でもある。
呪泉郷から帰って来て、今の俺は「男」に戻ってる。いや、それだけじゃねえ。傍らにはあかねが居る。紆余曲折あった後、今では格闘家「早乙女乱馬」の恋女房として、俺を脇から支えてくれている。
何だ、その、あいつが居るから俺はこうやって頑張れるわけで…。俺の片翼だ。
格闘家として注目を浴び始め、その世界ではちょっとしたスター。まあ、元々天賦の才があったからな。そっちで有名になることは大歓迎だ。だけど、知名度が上がるにつれ、それはそれで「厄介事」も増えてくるもの。
俺は芸能人じゃねえっつーのに、テレビやらマスコミやらに名前が挙がっていくものだから、前にも増して大騒ぎ。有名人は辛いぜっ…ってところで、あかねの姉貴、なびきが俺のマネージメントを一手に引き受けてくれている。昔から彼女はこういう企みごとには群を抜いた才能を持っていた。本能が金儲けへと素直に向かっていくのだ。
大学時代から徒党を組んでいたらしい九能先輩。九能家の豊富な財力をバックボーンに企画会社を作り、あれよあれよという間に大きくした。芸能プロダクションから企画物まで、業界を渡り歩く凄腕の女社長。それが今の天道なびきの肩書きだ。
アイドルとの醜聞だの、いらぬ好奇心の世間を渡るのに、彼女が味方に居ると確かに心強い。だが、腕が立つ分、面倒くさいこともある訳で。俺はマネージメントを一切頼んだ代償に、こき使われることもあるって訳。何某かのマージンは貰えるから、昔みたいな「ただ働き」が中心ではない。
格闘大会や武道の仕事なら、二つ返事で引き受ける俺だが、やれ、バラエティー番組に出ろだの、インタビューに答えろだの…そっちはどうしても好きになれねえ。避けたい仕事の一つであった。
「格闘家だって人気稼業なんだし、これはビジネスなんだからね。だから儲からないあんたのマネージメント受けてあげてるんだから、我慢なさいっ!」
と二言目には言われる。
儲からないとその辺りを強調したが、本当にそうなのかどうかは眉唾物だ。佐助さん辺りに聞くと、「乱馬殿が一番の儲け頭でござるよ。本当に助かるでござる。」なんて言ってたぜ。
まあいい。俺だって税金だの他に気を取られて、肝心な格闘をお留守状態にしたかねえから、多少の不備は我慢するべきだなと諦めて付き合う。
にしても、もうちょっと「金儲け」から離れてくれねえかなあ…。俺、曲がりなりにもおまえの妹の旦那、すなわち「義弟」なんだぜ。
「これが今度のインタビューの概要ね。ま、軽く目を通しておいて。」
何か書類らしいものをごそっと渡してくれる。
「それから、あかねにはちゃんと言っておいたから、あの子がコーディネイトした服、着て来なさいよ。この前みたいに道着なんかで来たらのしちゃうわよ。」
とさ。はあ、本当に面倒臭い。
書類にざっと目を通すと、ミセス向けの雑誌の記事。まああかねにコーディネイト頼むのは無難なところだな。格闘雑誌でビンビンのインタビューなら道着で撮影だっていいんだろうけどよ。
ん、待てよ、変なアイドルとの対談企画じゃねえだろうな。
この前はあの黒田んところの秘蔵っ子まなぴーの母親が相手でかなり焦りまくった俺。たくうっ!いくら仕事っつーたって、そういうのは勘弁して欲しいぜ。冷や汗ばかりが流れてきやがったし…。
それに、「早乙女乱馬、相原親子と和解か?」などと、穿ったゴシップ記者に暫く追い回されて迷惑だったんだからよう。
ありゃ一体全体何だったんだって、なびきに詰め寄ったら
『あっちサイドから申し込まれたのよ。話題作りよ、話題作り。あっちだってそろそろ話題になるソース欲しがってたし、いつまでも過去を引き摺っていがみ合ってあったって仕方ないじゃない。黒田だって、あたしの力認めざるを得なくなったようだし。ふふふ、まあ、この世界、持ちつ持たれつだからね。』
と簡単にいなされちまった。
『ギャラだって破格だったんだからさ。』
結局のところそこへ集約されるじゃねえかっ!
たはは、本当になびきの奴は金が大きく動くビジネスとなると目の色が変わる。そしてその犠牲者はいつも俺。
当日、言われた待ち合わせ場所に渋々出向く俺。
あんまり気乗りはしねえ。
あかねが選んでくれたのは、ごく普通の茶系のスーツ。黄色っぽいネクタイが派手と言えば派手かも。学生時代みたいにチャイナ服は普段着以外はあまり袖は通さない。ましてや、写真撮影を伴うような仕事なら余計に。
あ、おさげだけはそのままだ。
これは俺のトレードマークみてえなものだからな。しっかり連髪にして後ろで整えてる。心持、独身の頃よりおさげが長くなったかもしれねえ。
『ずっと髪の毛くくったままじゃ、禿るよ。』
なんて時々失礼な言葉をあかねが投げてくるが、寝るとき以外はこの髪型で通している。あ、昔は寝るときだっておさげのまんまだったが、最近はあかねの勧めで解いてる。あかねは相変わらず短いまんまだから、何だか夫婦で逆転した髪型だけれど、それはそれで気に入ってるんだ。寝床であかねが俺の髪の毛にもつれさせて絡ませる細い指。仕草がとっても可愛いんだぜ。
おっと、これ以上は夫婦の秘密事項。
カメラマンが適当なアングルからパシャパシャと写真を撮る。記事に使うんだろう。それからインタビューアーが入ってきた。それ相応にあちらさんが用意した女性。同世代の年恰好かな。でも、あんまり派手さは感じられなかった。
いや、初対面早々、ちょっとだけ違和感がしたんだ。
(どっかで会いましたっけ?インタビューのお姉さん。)
こういう仕事してるから、知らず知らずに顔あわせているかもしれねえ。
にっこりと微笑んでまずは自己紹介。
俺は女房以外の女には基本的には全く興味は持たない。どんな美人女優だってタレントだって同じ事。あかねに悪いと思うより、あかねより好い女はこの世に存在しないと思ってるからだ。美人だの容姿の端麗さだの、俺だって全くわからないわけではないが、俺にはあかねが居ればそれでいい。それだけは出会った頃からちっとも変わってねえ気持ちなんだ。
「今日はありがとうございます。」
インタビューは、無難に始まりやがった。
変に愛想の良い、姉ちゃんだなあ。ま、そんな感想を持った俺。
格闘界へ入ったことを中心に簡単な身上調査みたいなインタビュー。まずは無難にそんなところから入ってくる。聞き手によっては「いやらしさ」も感じられるが、今日の相手はそういう不快感は持たなかった。何でかすらっと話せる。初対面にしてはよう。きっとこいつもこの道のプロを自負してるんだろうな。
「で、奥様のことを少し…。」
ほら、来た。こういう女性向の雑誌は必ず訊いて来る。あかねとの馴れ初めのこと、そしてあいつと積み上げてきた格闘という世界のこと。
話題はどうしても二年前の無差別オール格闘技世界選手権大会のことへと向きたがる。まあ、世間の好奇をひきつけるのもわかるような気がする。
俺はあの大会の決勝戦をあかねと戦った。そして、勝利の後、そのままプロポーズへと持って行ったのだ。あまりのセンセーショナルな幕切れに、当時のマスコミはかなり盛り上がってくれたものだ。こっちは大騒ぎにする気なんざ全くなかったんだが、結果往来。
俺はただ、あかねに正直に己の気持ちを伝え、そして勢いでプロポーズしただけだったから。ずっと積もっていた想いが一気に噴き出した日。
真剣に戦った決勝戦。その戦いが終わったリングの上で痴話喧嘩をおっぱじめ、その上でプロポーズして、ご丁寧に誓いのキスまでしてしまったのだから、世間は好奇心でいっぱいなのだろう。
普通、好奇の目を向けるわな。自分のことじゃなかったら俺だって『良くやるぜ、ったく。このバカップルめっ!』と思うに違いねえもん。
「奥様はお元気でいらっしゃいますか?」
「ええ、まあ…。元気で格闘家、早乙女乱馬の嫁やってくれてます。」
とここでまた愛想笑い。
「学生時代、奥様かなりの不器用だって聞いてますけれど。」
一体全体、そんなこと何処で調べてくるんだろう。あかねが味音痴だったってことは、本当に周りに居た連中しか知らないはずなんだが。不思議だったが、適当に受け答えした。
「まあ、今はそれなりに何でもこなすようになってますよ。時々、とんでもない失敗料理作ることありますけどね…。」
そうなんだ。あかねはそれ相応に料理を作るようになっていた。あの超おぞましい味付けからは、何とか解放された。正直、あいつとの結婚生活に一抹の不安があったとすれば「食生活」のことくらいだったから、ホッとしたね。見目形は一歩譲れても、味だけは譲れないからな。味覚破壊されちまったら家庭だって崩壊しかねねーし。
とにかく人間が食えるレベルにはあがっていた。エサからは昇格だ。俺が修行に出ていた間、相当苦労はしたんだろう。
それでも時々変な失敗をやらかしてくれる。味はともかく見てくれは凄いこともある。あの不器用さは健在だ。
インタビューは様々、あかねのことに話題が及んだ。
世の奥様方は、本当にこんなインタビュー記事読みたいのだろうかと疑問を抱きつつも。しかし、このインタビューのお姉さん、良くした調べしてらあと舌を巻いたぜ。細かいこと良く知ってるんだ。
ちらっと後ろへ視線を流すとなびきがにんまりと微笑んでいるのが見えた。
もしかしたら、なびきか?情報元は。
金積まれたら、何でもじゃらじゃら喋っちまうかもしれねえな、あの女は。
「最後に、奥様を花に喩えてみてくれませんか?奥様は早乙女乱馬さんから見て、どんな花に喩えられるか。これはこの連載記事のお約束事みたいなインタビューですから。」
なるほどな。だから花のインタビューってんだ。
「やっぱり、「白木蓮(マグノリア)」ですか?」
と先方は振ってきた。
白木蓮はあかねが俺と闘ったときのリングネームだ。可憐なマスクをつけて、あいつは俺と対峙するために戦い抜いた。
凛と強く咲いたリングの仇花。それが「白木蓮」だった。
確かに思い出の花の名前には違いないが、俺はゆっくりと首を横に振った。
「いいえ、俺の中のイメージでは、マグノリアじゃありません。」
「じゃあ、どんな花なんでしょう。興味がありますね。」
俺は少し考えを巡らせると、ゆっくりと言葉を継いだ。
「あえて喩えるなら「紫式部」でしょうか。」
「紫式部?」
司会者はへっというような顔をした。
「俺が喩えたいのは花枝より、実を付けた姿なんですけどね。」
そうだ。
この国には紫式部という名前の低木が自生している。春先に淡い紅色の花を咲かせ、そして秋になるとそのすっと伸びた枝先にたわわに小さな紫色の実を実らせる。
その実の鮮やかな紫から、かな文学華やかなりし頃の「源氏物語」を書いた女流作家、紫式部にちなんだ名前がつけられた。
秋になると落葉しながら、美しい紫色の実が葉先から光るのだ。
派手さはないが、しっとりとした秋に栄える植物だ。花よりも実の方が印象的な姿をしていて、鑑賞の対象になる。
すっと脇からアシスタントが、植物図鑑を持ってきて広げた。どうやら、このインタビューの姉さん、紫式部を知らなかったらしい。
「この美しい枝葉の紫式部ですか…。奥様を喩えるなら。」
少し溜息が漏れた気がする。
何で俺がこんな植物を知ってたかって?
まあ、その…。天道家の庭の隅っこに植わっていたのを知ってたんだ。普段は目立たないこの低木も、秋になると美しい実をたわわにつける。その姿かたちが何故かしら可憐に見えた。
身体を思い切り動かして、疲れを感じたとき、ふっと目を落として見つける可憐な実。何故だろう、あかねに似ていると思ったのだ。
勿論、花の名前は知らなかった。後でお花の師範免許を持っているおふくろに「紫式部」とか「紫重実(むらさきしきみ)」とか呼ばれていることを教えてもらった。
「決して派手さはないんですが、居候していた庭先で実をつけている姿が印象的で…。その頃から気になってた少女に似てるってずっと思ってたんです。」
「その少女が奥様だったわけで?」
「俺にとってあいつは初恋の女性でもありますから…。」
俺は誘導されることなく、自分でその想いを言葉に紡ぎだす。ごく自然に流れた言の葉だ。
「紫の美しい枝葉が彼女の横顔に重なるんです。儚げでいて、守ってやりたいってね…。そうやって俺は強くなってきたわけですから…。」
あかねが居たから俺は強くなれた。勿論、これからも。
男は守りたいと思う女ができてこそ、より強くなれるのだと思う。
「彼女への想いが今の俺を象ってきたようなものですから…。」
まあ、こんな記事、あかねには見せられねえな。照れくさくって。
「今日はどうもありがとうございました。」
インタビューは終わった。周りを取り巻いていたカメラさんや録音技師もバタバタと片付けに入る。
「本当、ありがとう、早乙女君。」
今しがたまで俺へインタビューしていた女性がにっこりと微笑んだ。
「あん?」
名前に君付けってちょっとなれなれしくねえかと言わんばかりに俺が顔を上げると、続けざまにそのお姉さんは言った。
「そっか…。やっぱあかねが初恋だったか。納得しちゃったわ、あたし。」
いきなりさばけてきやがる。何なんだと思って無言で顔を覗いた。
ん?やっぱりどっかで会ったことあるかあ?
「あんたが風林館に転校してから、あかねも変わったものね…。でも、突っ張ってたあの頃からずっとあかねのこと大切に見てたんだ、早乙女君は。」
ちょっと待て。今何っつった?風林館?転校?…
「あー、おめえっもしかしてっ!!」
俺は指を出したまま固まっちまった。
「あら、今頃気が付いたの?乱馬君。」
「てめえっ!ゆか…か?」
口はあんぐり。あかねの親友で俺ともクラスメイトで…。
「ホント、あかね以外の女性は全然目に入ってないのねえ…。ちゃんと結婚式にも呼ばれてたんだけどな…。」
「だってよ…。おめえ、髪の毛染めてるし、化粧も濃いし…。」
「ちょっとっ!その言い草はないでしょう?あたし、今でもあかねとは親しんだぞ…。」
げ…。そうとわかってたら、もうちょっと…。お、おれ、何口走った?え…。何訊かれてた?
だんだん頭がパニックになってくる。ぐるぐる記憶が巡りだす。
「紫式部にあかねを喩えるなんて、ねえ…。渋いんだ。乱馬君って…。それより、やっぱ、ずっとあかねのこと見てきたんだねえ。みんなの前では思いっきりあかねのことけなしまくってたくせに…。」
「うっせーっ!ゆか、このことはあかねにはナイショ…。」
ゆかが思い切り笑い出した。
「ナイショになんかできるわけないじゃないの。これ、仮にもインタビュー記事にしなくっちゃいけないんだからあ。記事になったらあかねも読むわよ。」
「だあっ!駄目だ。読ませねえ。」
「そう言うわけにはいかないんじゃないの?印刷されたら否が応でも目に入るわよ。」
はあ、やぶへびだあ。何でこうなるんだよ。
そっか、やけにいろいろと詳しいと思ったら、ゆかだったのか。
芸名って奴でレポーターしてたから全然気がつかなかったぜっ!!不覚だった。
後ろ振り返ると、なびきがくくくと笑いをぶちまけてやがった。
畜生っ!なびきの奴にはわかってたんだな。ゆかがインタビューを担当するって。
だが、もう後の祭り。きっと記事がいくつかカットされたとしても、ゆか本人からあかねに全部筒抜けになる…。記事もきっとゆかの解説つきで。
次の月、雑誌は発売になった。
「紫の君へ…。」
そんな見出しが踊っていた。
暫く、親父や良牙たちの酒の肴にされまくったのは言うまでもなく…。
その影であかねは妙に機嫌が良かったような気がする。
秋も深まって、庭先の紫式部の葉はすっかり落ち、実がさらに美しく光って見える。俺は自分に課していたトレーニングを終えると、庭先に洗濯物を干しに来たあかねに言った。
「なあ、あかね…。」
俺はそのたわわな枝先に落とした目を転じ、あかねをふり返った。
「そろそろ…。子供作らねーか…。家族が増えてもいいなって…。その。」
恐々切り出す。
「そうね…。花はいつか実を結ぶものだものね…。」
そういうこと。やっぱりおまえと俺の血が繋がった実をこの胸に抱いてみたい。俺たちの想いを次へと受け継ぐ実を…。
俺は細い彼女の肩へ手を伸ばすと、そっと唇を合わせた。可憐な紫の君に。
完
紫式部。ムラサキシキミ、ミムラサキという別名も。
クマツヅラ科の落葉低木で、秋になると美しい紫色の実をたわわに枝につける。
花言葉は「上品」「聡明」。やっぱりあの紫式部にちなんでつけられてるのかな。
一之瀬家の猫の額庭先にもひっそりと植わっています。私が好きな低木なので植えてもらいました。
(c)Copyright 2000-2005 Ichinose Keiko All rights reserved.
全ての画像、文献の無断転出転載は禁止いたします。